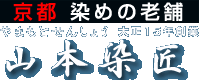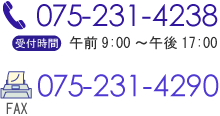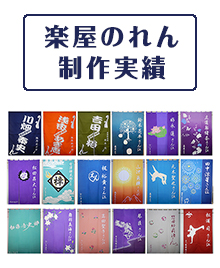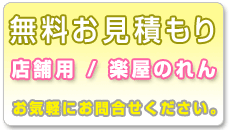![]()
山本染匠では伝統的な技法により、ご注文いただいてから白生地よりお好みのデザインに染め上げ、各工程を一貫しています。
最初のお打ち合わせよりご希望される完成形をお聞かせください。何もわからない場合でも順番にご説明させていただきます。
一工程ずつ、丁寧に確実に、質の高いもの創り上げております。
何よりもご依頼いただいた方へ、また実際に暖簾を使用いただける方に喜んでいただけるよう一生懸命取り組みさせていただきます。

【店舗のれん】 → 店舗のれん制作実績
見た目の美しさもあり看板の代わりになる「のれん」。
商売をされている皆様においては、まさしく店の顔です。
だからこそ納得のいく「のれん」をご提供できるようにお手伝いさせていただきます。オリジナルデザイン、色目、素材などお気軽にご相談ください。

【楽屋のれん】 → 楽屋のれん制作実績 01
楽屋にの前につるす「楽屋のれん」は歌舞伎役者、舞台俳優、日本舞踊など、なくてはならないものです。
ごひいきの役者さんに心のこもった「楽屋のれん」を贈られると大変喜ばれます。

【湯のれん】→ 湯のれん制作実績
「湯のれん」は、旅館などで目にするだけで、誰もがいざなわれる「癒し」の空間です。
「湯殿」がいくら凝った作りでも、「湯のれん」をくぐらなければ「温泉」という「舞台」の幕はあきません。
のれん豆知識
▼ のれんの形
通常、暖簾の標準布丈は、昔風にいえば鯨尺の3尺、今風にいえば1m13cm。
標準布丈の半分、要するに1尺5寸、56.7cmのものを「半のれん」と呼ばれます。
そば屋、すし屋、お好み焼き屋などの飲食店が多く店舗入り口に掛け、今日まで続いています。暖簾を分けて入るというより、暖簾をくぐるといった感じの丈です。
4尺2寸、1m60cmのものが「長のれん」。
出入口いっぱいに掛ければ目隠しの役目を、商品などを置いた台の前に掛ければ日除けの役目をはたしています。
布丈40cmほどのものを間口いっぱいの軒先に張ったものが「水引のれん」。
当初は「水引のれん」は切り込みのない幕形式で、塵除けが目的だろうとされています。
大風呂敷のような一枚の布を上端しを軒先に、下端しを道路にせりだたせて固定した暖簾を「日除けのれん」と呼びます。風にあおられると、パターンと音がすることから「太鼓のれん」とも呼ばれている暖簾です。
暖簾は店の入口にかけられることで客に店の存在やテーマを示し、また外からの視線を遮ることで内部のプライバシーを守る役割も果たします。さらに季節やイベントに合わせてデザインを変えることで店の雰囲気を変化させることも可能です。
▼ のれんの発祥地
・ 日本でののれんの発祥は古く、平安時代頃とされ暖簾発祥の地は京都と言われています。昔から日本の伝統文化や風習を感じさせる装飾品としても親しまれています。
▼ のれんの染色
・ 紺、藍色は手堅さを身上とした商家が多く、特に藍の匂いを虫が嫌うとして
呉服屋の多くが藍染を使用しました。
・ 柿色は遊女屋など水商売に多い。
・ 白地に印を墨書きにしたものは菓子屋、薬屋に多い。
・ 茶色は煙草屋が多い。
・ 紫色は昔は「禁色」として、のれんには使えない色でした。
▼ のれんの文字
・ 商家ののれんに店印などの模様が描かれるようになったのは鎌倉時代といわれている。
・ 文字が書かれるようになったのはさらに時代がすすんだ江戸時代初め頃とされている。
・ この文字入りののれんが普及の要因は庶民の識字力の向上である。
・ 庶民の識字能力が低かった鎌倉、室町時代はのれんが目的としての役割を果たすには色や模様に頼るほかなかった。
▼ 石川県金沢市を中心とした加賀、能登地方の「花嫁のれん」
石川県金沢市を中心とした加賀・能登地方には、嫁入り道具のひとつとして
美しい「花嫁のれん」を持参する風習があります。
縮緬や羽二重の生地を用い、宝船、鶴亀、松竹梅、鳳凰、おしどりなど、おめでたい絵柄を染め、花嫁の家紋を入れた「花嫁のれん」。
「花嫁のれん」は婚礼の日から一週間くらい若夫婦の部屋の入口にかけられたあと、末永く箪笥の底に納められる。一生に一度しか飾られることがない暖簾であるが「花嫁のれん」をくぐったときから新しい女の一生の始まり、次なる人間のドラマの幕開けとされています。
加賀百万石、前田家三百年の城下町であった北陸の古都金沢、この地方に残る「加賀のれん」のように、座敷と奥座敷の堺に掛けられる長のれんを「床のれん」または「座敷のれん」と呼びます。
奥座敷を見せないための間仕切り、装飾を目的とした「床のれん」の場合、
一般的に総柄風の絵のれんが多くあります。
▼ 結界の美
「楽屋のれん」は楽屋と舞台の結界です。
女は「花嫁のれん」をくぐったとき、娘から嫁にかわり、
商家の暖簾をくぐったとき、人はお客様へかわります。
暖簾は異なった二つの世界えを隔てる、または結ぶと考えるとき、
暖簾と結界の相互関係がそれほど不自然でないことです。
弊店「山本染匠」の職歴内容
・ 昭和天皇の風呂敷
・ 現天皇皇后両陛下の夜具
・ 三笠宮殿下の風呂敷
・ 表千家、裏千家のお家元の風呂敷
・ 衆・参両議院の袱紗
・ 迎賓館の茶席座布団
・ 歴代の横綱の関取用座布団
・ 幕内力士の関取用座布団
・ 歌舞伎役者の楽屋のれん・座布団
・ 有名舞台役者の楽屋のれん
・ 各宗派総本山の風呂敷
・ 菊正宗などのCM用の風呂敷
・ イエテボリ世界陸上選手権の招待選手への粗品(ランチョマット・コースター)
・ 他多数 制作
- 京都 山本染匠ご連絡先 -
【弊社染め工房の地図】
工房へお越し頂く際はマップより
場所をご確認くださいませ。
山本染匠の伝統技法・印染め
テレビNHK教育放送番組「美の壺」にて弊社代表・山本昌宏が取材を受け、08年6月に放送されました。


当店のオリジナル暖簾(店舗・楽屋)
お見積もりやお問合せはお気軽にどうぞ。